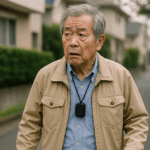この記事で分かる事、ポイント
- 子どもの防犯対策 登下校で親が意識すべきこと
- 通学路の危険箇所を把握し、子どもと共有する方法
- 不審者への具体的な対応策と危険回避の訓練
- 効果的な防犯グッズの選び方と使い方
- 家庭での防犯ルール作りとコミュニケーションの重要性
- 地域全体で子どもを見守るための連携方法
- 子どもの危機管理能力を高めるためのシミュレーション
子どもの防犯対策 登下校に不安を感じている保護者の方も少なくないでしょう。毎日送り出す大切な子どもたちが、安全に学校へ行き、無事に帰ってくることは親として最も願うことですね。しかし、残念ながら現代社会では、子どもを狙った犯罪やトラブルが後を絶ちません。
このような状況を考えると、ただ「気をつけてね」と声をかけるだけでは不十分だと感じています。親が具体的な知識を持ち、子どもと一緒に防犯意識を高めることが何よりも大切だと考えられます。では、一体どのような対策を講じればよいのでしょうか。
この記事では、子どもの防犯対策 登下校において親ができること、子ども自身が身につけるべきこと、そして地域全体で取り組むべきことについて、多角的な視点から詳しく解説していきます。具体的な危険箇所の把握から、いざという時の防犯グッズの活用、さらには地域との連携による見守り活動まで、網羅的に情報を提供しています。
この記事を読み終える頃には、お子さんの登下校における安全を守るための具体的な行動計画が立てられるようになっているでしょう。そして、何よりも子どもたちが安心して学校生活を送れるように、私たち大人ができることを見つけ、実践するきっかけとなれば幸いです。一緒に子どもの安全を守るための知識を深めていきましょう。
子どもの防犯対策 登下校で身を守るための意識づくり
この章のポイント
- 危険箇所を事前に把握する重要性
- 不審者への対応と具体的な回避行動
- 防犯グッズの活用と選び方のポイント
- 危険回避のためのルール作りと声かけ訓練
- 万が一に備えたシミュレーションの実施
危険箇所を事前に把握する重要性

子どもの防犯対策 登下校において、まず最初に取り組むべきことは、通学路の危険箇所を特定し、親子で共有することでしょう。通学路には、死角になりやすい場所や人通りが少ない道、工事現場や空き家など、子どもが犯罪に巻き込まれるリスクが高まるスポットが潜んでいます。
私の経験上、親が「ここは危ない」と考えていても、子どもにとっては遊び場や近道として認識されているケースも少なくありません。そのため、単に「危ないから気をつけて」と伝えるだけでは不十分だと考えられます。
具体的には、まず親が実際に子どもの通学路を歩き、危険だと思われる場所をリストアップしてみましょう。例えば、薄暗い道や見通しの悪い交差点、放置自転車が多い場所、人目のつきにくい公園の出入り口などが挙げられます。こうした場所を特定したら、次に子どもと一緒に歩いて、それぞれの場所でどのような危険が潜んでいるのか、どのように行動すべきかを具体的に話し合うことが大切です。
このとき、地図アプリなどを活用して危険箇所をマークし、それを親子の間で共有するのも有効な手段だと思われます。また、子どもが「この道は怖い」と感じる場所があれば、その気持ちをしっかりと聞き入れ、代替ルートを一緒に考えることも重要でしょう。時には、遠回りになっても安全な道を選ぶ勇気を教えることも必要になってきます。
- 親子で実際に通学路を歩く
- 危険な場所(死角、人通りの少ない道、工事現場など)を特定する
- なぜ危険なのか、どのように行動すべきかを具体的に話し合う
- 地図アプリなどを活用して危険箇所を共有する
- 子どもが怖いと感じる場所があれば、代替ルートを一緒に検討する
これらの取り組みを通じて、子どもは自ら危険を察知し、判断する能力を養うことができます。親の「危ない」という言葉だけでなく、子ども自身が「なぜ危ないのか」を理解することで、より深く防犯意識が根付くのではないでしょうか。常に通学路の状況は変化するものですから、定期的に確認し、新しい危険がないか目を光らせることも親の役割です。
不審者への対応と具体的な回避行動
子どもの防犯対策 登下校において、不審者との遭遇は最も避けたい状況の一つです。しかし、万が一遭遇してしまった場合に備え、子どもに具体的な対応策を教えておくことは極めて重要だと言えるでしょう。単に「知らない人にはついていかない」という漠然とした指示だけでは、子どもは具体的な行動に移せない可能性があります。
私が考えるに、子どもに教えるべきは「具体的な危険回避の行動」です。例えば、「もし知らない人に声をかけられたらどうする?」と問いかけ、様々なシチュエーションを想定してロールプレイングを行うのは有効な方法です。このとき、「逃げる」「大声で助けを求める」「近くの大人に知らせる」といった基本的な行動パターンを繰り返し練習することが肝心です。
具体的には、「いかのおすし」といった防犯標語を子どもと一緒に確認し、その意味を深く理解させることが大切ですね。「いかない」(知らない人についていかない)、「のらない」(知らない人の車に乗らない)、「おおごえを出す」(危険を感じたら大声を出す)、「すぐに逃げる」(すぐにその場から逃げる)、「しらせる」(近くの大人や警察に知らせる)という五つの行動は、子どもにとって覚えやすく、いざという時に役立つでしょう。
また、大声を出す練習も欠かせません。多くの子どもは、普段から大声を出すことに慣れていないため、いざという時に声が出ないことがあります。自宅で「助けて!」や「やめて!」といった声を出す練習を一緒にしてみるのも良いでしょう。近所の人に、子どもがもし大声を出していたら注意して見てほしいと伝えておくことも、地域連携の一環として考えられます。
不審者から身を守るためには、まずは距離をとり、相手の車や名前、特徴などを冷静に覚えておくことも重要です。しかし、それ以上に、命を守るための「逃げる」という行動を最優先させるべきだと考えられます。子どもが安心して行動できるように、具体的な回避行動を教え、繰り返し練習することが、親の務めだと感じます。
防犯グッズの活用と選び方のポイント
子どもの防犯対策 登下校を考える上で、防犯グッズの活用は非常に効果的な手段の一つです。しかし、ただ持たせるだけでなく、その選び方や正しい使い方を子どもに教えることが肝心でしょう。
代表的な防犯グッズといえば、やはり「防犯ブザー」ですね。防犯ブザーは、大音量で周囲に危険を知らせ、不審者をひるませる効果が期待できます。しかし、大切なのは、電池切れがないか定期的に確認することと、いざという時にすぐに鳴らせる場所に装着しておくことです。ランドセルの奥底に入れていては意味がありません。ストラップで常に手の届く場所に付けておく、あるいはネックストラップで首から下げておくなど、子どもがとっさに使えるような工夫が必要だと言えるでしょう。
また、GPS機能付きの携帯電話やスマートフォンも、子どもの位置情報を把握できるため、親にとっては安心材料となります。ただし、子どもが常に持っているとは限らないことや、バッテリー切れのリスクも考慮する必要があります。そのため、学校や習い事への持ち込みルールを確認し、適切なタイミングで充電する習慣をつけさせることも大切でしょう。現在では、GPS機能に特化した小型の見守りデバイスも登場しており、携帯電話を持たせたくない家庭にも選択肢が広がっています。
他にも、反射材付きのキーホルダーやステッカーも有効です。これは、車のライトに反射して子どもの存在を知らせることで、交通事故のリスクを減らすだけでなく、暗い場所での不審者対策にもつながります。夜遅くまで塾や習い事がある場合は、特に重要だと考えられます。
- 防犯ブザー:電池の定期確認とすぐに鳴らせる位置に装着
- GPS機能付きデバイス:位置情報把握、バッテリー管理、持ち込みルールの確認
- 反射材:交通事故防止、暗い場所での視認性向上
防犯グッズはあくまで補助的なものです。最も重要なのは、子ども自身の防犯意識と、それらを効果的に使えるかどうかだと考えられます。親としては、子どもと一緒に防犯グッズを選び、使い方を練習し、その重要性を伝えることが大切でしょう。
防犯ブザーの正しい使い方
防犯ブザーは、ただ持っているだけでは意味がありません。いざという時に確実に作動させ、効果を発揮できるように、正しい使い方を子どもに教えておくことが重要です。
まず、防犯ブザーの「作動方法」を理解させることから始めましょう。多くのブザーはピンを引き抜く、またはボタンを押すことで鳴る仕組みになっています。子どもが緊張していても、とっさに操作できるようなシンプルなタイプを選ぶのが望ましいでしょう。
次に、「どのような状況で鳴らすべきか」を具体的に教える必要があります。例えば、不審な人に声をかけられたり、つきまとわれたり、腕を掴まれたりした時など、具体的なシチュエーションを想定して説明することが大切です。「怖いと感じたら、ためらわずに鳴らすこと」というメッセージを明確に伝えましょう。
そして、最も重要なのは「鳴らしたらすぐに逃げる」という行動です。ブザーを鳴らして不審者がひるんだ隙に、人通りの多い場所や近くのお店、自宅など、安全な場所に逃げ込むよう指導してください。ブザーはあくまで注意を引くためのものであり、不審者を完全に撃退するものではないことを理解させる必要があります。
また、定期的な「点検」も欠かせません。電池が消耗していないか、ブザーが正常に鳴るかなどを、月に一度は親子で確認する習慣をつけましょう。いざという時に電池切れでは、子どもの命を守る大切な道具が意味をなさなくなってしまいます。これらの正しい使い方と点検を通じて、防犯ブザーを子どもの安全を守る頼れる味方として活用できるようになるでしょう。
危険回避のためのルール作りと声かけ訓練

子どもの防犯対策 登下校において、家庭内でのルール作りは非常に重要な役割を果たします。具体的な行動指針を明確にすることで、子どもは迷わず適切な判断を下せるようになるでしょう。曖昧な指示では、子どもが危険な状況に直面した際にどうすれば良いか分からなくなってしまう可能性があります。
私が考えるに、まず「知らない人にはついていかない」「知らない人の車に乗らない」といった基本的なルールを徹底することが肝心です。しかし、これだけでは不十分で、「もし知らない人に名前を呼ばれたらどうする?」「知り合いを装って近づいてきたら?」など、より具体的なシチュエーションを想定したルール作りが必要です。
例えば、「危ないと思ったら大声で助けを求めること」「近くのお店や『こども110番の家』に駆け込むこと」「すぐに親に連絡すること」といった行動を、具体的にルールとして定めるべきです。このとき、これらのルールを一方的に押し付けるのではなく、子どもと一緒に話し合い、納得の上で決めることが大切でしょう。子ども自身がルール作りに参加することで、主体的に防犯意識を高めることにつながると考えられます。
- 知らない人には絶対についていかない
- 知らない人の車には絶対に乗らない
- 危険を感じたら大声で助けを求める
- 「こども110番の家」や近くのお店に駆け込む
- 何かあったらすぐに親に連絡する
さらに、これらのルールを実践するための「声かけ訓練」も非常に有効です。親が不審者役となり、子どもに声をかけられた際の対応をロールプレイングで練習するのです。この訓練を通じて、子どもは実際に大声を出す練習ができ、いざという時に声が出やすくなるでしょう。
訓練の際には、「『やめて!』『助けて!』と叫ぶこと」や「防犯ブザーを鳴らすこと」をセットで行うように指導してください。また、訓練後には必ず子どもを褒め、恐怖心を煽るのではなく、「もしもの時に身を守るための大切な練習だよ」とポジティブなメッセージを伝えることが大切です。これにより、子どもは防犯意識を自然に高めていくことができるでしょう。
万が一に備えたシミュレーションの実施
子どもの防犯対策 登下校をより実効性のあるものにするためには、単に知識を与えるだけでなく、万が一の事態に備えた具体的なシミュレーションを親子で実施することが非常に効果的です。子どもたちは、頭で理解するよりも、実際に体を動かして体験することで、より深く学び、記憶に定着させる傾向があるからです。
私が考えるに、シミュレーションは、「もし不審者に遭遇したら?」という架空の状況を設定し、子どもがどのように行動するかを実践的に試す機会となります。例えば、通学路の途中で親が隠れて声をかけ、子どもがどう反応するかを観察してみましょう。このとき、子どもが指示通りに大声を出したり、逃げ出したりできるかを確認します。</p{marker}>そして、うまくいかなかった点があれば、その場で具体的なアドバイスを与え、改善策を一緒に考えることが大切です。
シミュレーションの対象は不審者対策だけに限りません。例えば、「地震が起きたらどうする?」「急な大雨で通学路が冠水したら?」といった自然災害への対応も、シミュレーションを通じて学ぶことができます。事前にハザードマップを確認し、安全な避難経路を親子で確認しておくことも、いざという時の危機管理能力を高める上で非常に重要だと言えるでしょう。
このシミュレーションは、決して子どもを怖がらせるためのものではありません。むしろ、様々な状況を経験することで、子どもが自信を持って行動できるようになるための練習だと捉えるべきです。練習を重ねることで、子どもは「もしもの時でも、自分はこうすれば大丈夫だ」という安心感を抱くことができるでしょう。
- 不審者遭遇時のロールプレイング
- 自然災害発生時の避難行動確認
- 防犯ブザーの使用練習
- 安全な場所への駆け込み練習
- 親への連絡方法の確認
シミュレーションは一度行ったら終わりではなく、定期的に、そして子どもの成長に合わせて内容を更新していくことが望ましいです。特に、新学年になったり、新しい習い事を始めたりして、通学路や生活環境に変化があった際には、再度シミュレーションを行うことをお勧めします。これにより、子どもの防犯対策 登下校は常に最新の状態に保たれることになるでしょう。
家庭と地域が連携する子どもの防犯対策 登下校
この章のポイント
- 地域連携で安全な通学路を確保する
- 親の役割と子どもとのコミュニケーション
- 家庭でできる防犯対策の見直し
- 防犯意識を高める地域の見守り活動
- 子どもの防犯対策 登下校で実践すべきこと
地域連携で安全な通学路を確保する

子どもの防犯対策 登下校は、家庭内での努力だけでは限界があります。子どもたちの安全をより強固なものにするためには、地域全体で連携し、安全な通学路を確保する取り組みが不可欠だと言えるでしょう。地域社会の一員として、私たち大人が積極的に関わることが求められています。
私の視点では、まず学校や地域の自治体と連携し、通学路の危険箇所を共有する場を設けることが重要です。定期的な「通学路合同点検」を実施し、防犯カメラの設置状況や街灯の明るさ、死角になる場所の有無などを確認する機会を設けてみてはいかがでしょうか。これにより、具体的な改善策を地域全体で検討し、実行に移すことが可能になります。
また、「こども110番の家」のような地域の協力体制を積極的に活用することも大切ですね。これは、子どもが危険を感じた際に駆け込める安全な場所を提供する制度です。地域住民が協力して子どもたちを見守る意識を持つことは、不審者に対して「この地域は子どもたちを孤立させない」という強いメッセージを送ることにもつながります。
- 学校や自治体との連携強化
- 定期的な通学路合同点検の実施
- 「こども110番の家」の積極的な活用
- 防犯カメラや街灯などインフラの改善
- 地域住民による見守り活動への参加
さらに言えば、地域で開催される防犯訓練や防犯教室に積極的に参加することも、地域全体の防犯意識を高める上で非常に有効です。親だけでなく、地域のお年寄りやお店の人々も巻き込み、地域全体で子どもたちの安全を守るという共通認識を持つことが、最も効果的な子どもの防犯対策 登下校へと繋がると考えられます。地域が一丸となって見守る体制は、子どもたちにとって何よりも心強い存在となるでしょう。
親の役割と子どもとのコミュニケーション
子どもの防犯対策 登下校において、親の役割は非常に大きく、特に子どもとの日頃からのコミュニケーションがその基盤となります。単に危険を伝えるだけでなく、子どもが安心して相談できる関係性を築くことが何よりも大切だと考えられます。
私が経験した中では、子どもが危険な目に遭った時や不安を感じた時に、「親に話しても怒られないか」「心配をかけるのではないか」と躊躇してしまうケースがあります。このような状況を避けるためにも、親は常に子どもの話に耳を傾け、どのような内容でも真剣に受け止める姿勢を示すべきでしょう。
具体的には、毎日「今日は何か変わったことはあった?」「学校帰りに怖いことや嫌なことはなかった?」といった声かけを習慣にしてみましょう。このとき、単なる形式的な質問ではなく、子どもの目を見て、共感的な態度で話を聞くことが重要です。子どもが話したがらない場合は、無理に聞き出そうとせず、いつでも話して良いという安心感を与えることが大切だと言えます。
また、防犯に関する話題を日常会話の中に自然に組み込むことも有効です。例えば、ニュースで不審者に関する報道があった際に、「これを見てどう思った?」「もしあなただったらどうする?」といった問いかけを通じて、子どもの防犯意識を高める機会とすることもできます。決して子どもを怖がらせるのではなく、あくまで「自分の身を守るための知識」として伝えることが重要だと考えられます。
さらに、親自身が地域の防犯活動に積極的に参加する姿を見せることも、子どもにとって良い教育になります。親が地域の人々と協力し、子どもの安全を守ろうとしている姿は、子どもに安心感を与え、地域全体への信頼感を育むことにもつながるでしょう。このように、親子のコミュニケーションを密にし、地域との連携を図ることで、子どもの防犯対策 登下校はより効果的なものになると考えられます。
子どもが親に相談しやすい環境づくり
子どもが安心して危険な出来事を親に話せる環境を作ることは、防犯対策において非常に重要です。もし子どもが「こんなことを話したら怒られるかも」と感じてしまえば、本当に困った時に声を上げることができません。
まず、日頃から「何でも話していいんだよ」「どんなことでも、お父さんやお母さんはあなたの味方だから」というメッセージを伝え続けることが大切です。子どもが何かを打ち明けてきた時には、その内容がたとえ些細なことや、親から見て「なぜそんなことをしたのか」と思うようなことであっても、まずは子どもの話に最後まで耳を傾け、共感する姿勢を見せましょう。
感情的に反応せず、まずは「大変だったね」「怖かったね」といった言葉で子どもの気持ちを受け止めることが、信頼関係を深める上で不可欠です。その後で、冷静に事実確認を行い、必要であればアドバイスを与えるようにしましょう。この順番を間違えると、子どもは口を閉ざしてしまう可能性があります。
また、子どもが自分から話さない場合でも、親の方から積極的に「今日あったことで、何か話したいことはある?」と声をかけたり、一緒に遊んだりする時間を作ることで、子どもが安心して話せる機会を増やしていくことができます。特に、寝る前の時間や食事の時間など、リラックスできる時に軽い会話から始めるのも良い方法でしょう。
このような日々の積み重ねが、子どもにとって「親はいつでも自分の味方であり、どんなことでも相談できる存在だ」という確信に繋がり、いざという時にためらわずに助けを求める勇気を与えることになります。子どもが親に相談しやすい環境は、子どもの防犯対策 登下校の要だと言えるでしょう。
家庭でできる防犯対策の見直し
子どもの防犯対策 登下校を考える際、家庭内でできる対策は多岐にわたります。定期的にこれらの対策を見直し、子どもだけでなく家族全員で防犯意識を高めることが重要だと考えられます。
まず、基本的なことですが、自宅の防犯対策は万全でしょうか。子どもが留守番をする機会がある場合、鍵の閉め方や来客対応について具体的に教えておく必要があります。不審者が自宅に侵入しようとするケースも少なくありません。ドアや窓の施錠はもちろんのこと、インターホン越しに知らない人には安易に対応しない、親が帰るまではドアを開けないといったルールを徹底させましょう。
次に、緊急時の連絡方法を明確にしておくことが大切です。親の携帯電話番号はもちろん、祖父母や近所の信頼できる大人の連絡先を、子どもがいつでも確認できる場所にリストアップしておきましょう。また、携帯電話を持たせている場合は、緊急時の連絡先を登録し、いざという時にすぐにかけられるように練習しておくことも重要です。
さらに言えば、インターネットの利用についても注意が必要です。子どもがSNSなどで個人情報を安易に公開してしまうと、そこから行動パターンが特定され、登下校時に狙われるリスクもゼロではありません。家庭内でインターネットの利用ルールを設け、安易な情報公開をしないよう指導することも、間接的な子どもの防犯対策 登下校につながると考えられます。
これらの対策は、一度行ったら終わりではありません。子どもの成長に合わせて、その都度見直し、新たな危険がないかを確認していく必要があります。特に、子どもが小学校から中学校に進学する際など、行動範囲が広がるタイミングでは、再度家族で防犯対策について話し合う機会を設けるべきだと感じます。
- 自宅の施錠と来客対応ルールの徹底
- 緊急連絡先の共有と連絡方法の練習
- インターネット利用における個人情報保護の指導
- 子どもの成長に合わせた防犯対策の見直し
- 家族全員での防犯意識の共有
家庭全体で防犯意識を高め、子どもが安心して過ごせる環境を整えることが、結果として安全な登下校にも繋がるのではないでしょうか。
防犯意識を高める地域の見守り活動
子どもの防犯対策 登下校は、個々の家庭や学校任せにするのではなく、地域全体で子どもたちを見守る「地域の目」を増やすことが非常に効果的です。多くの大人が通学路に目を配ることで、不審者が近寄りにくい環境を作り出すことができるでしょう。
私の視点では、まず地域住民が主体となって行われる「登下校時の見守り活動」への参加を検討することです。これは、ボランティアとして子どもたちの登下校時間に合わせて通学路に立ち、見守りを行う活動ですね。毎日でなくても、週に数回、数十分でも参加する人が増えれば、子どもたちにとっては大きな安心感につながります。
また、地域の商店や企業に「こども110番の家」や「安全の家」としての協力を呼びかけることも有効だと考えられます。これらの目印があることで、子どもたちは危険を感じた際に安心して駆け込める場所を事前に把握できます。地域のお店の人々が日頃から子どもたちに目を配り、時には声かけを行うことで、地域全体に温かい見守りの輪が広がるでしょう。
さらに、地域住民同士のコミュニケーションを活発にすることも大切です。例えば、地域のイベントや町内会を通じて、顔見知りの大人が増えれば、いざという時に助けを求めやすくなります。見知らぬ人ばかりの地域よりも、顔の見える関係性が築かれている地域の方が、不審者が活動しにくい環境だと言えるでしょう。
- 登下校時の見守り活動への参加
- 地域の商店などへの協力依頼(こども110番の家など)
- 地域住民同士のコミュニケーションの活性化
- 地域安全マップの作成と共有
- 防犯パトロールの実施
最近では、スマートフォンのアプリを活用して、地域の見守り情報を共有する取り組みも増えています。不審者情報や危険箇所の情報をリアルタイムで共有することで、地域全体の防犯意識をより高めることができるでしょう。地域全体で見守る目は、子どもの防犯対策 登下校を支える強力な力になると言えます。
子どもの防犯対策 登下校で実践すべきこと
子どもの防犯対策 登下校に関して、これまでに様々な視点から解説してきましたが、最終的に親として「何を実践すべきか」を具体的にまとめることが大切ですね。情報が多すぎると、どこから手をつけて良いか迷ってしまうかもしれません。そこで、ここでは実践すべきことを簡潔に整理してご紹介します。
まず、最も基本となるのが「子どもの通学路を親子で歩き、危険箇所を把握し共有する」ことです。これは、子ども自身の危険察知能力を養う上で不可欠なステップだと言えるでしょう。地図に危険箇所をマークしたり、具体的な回避方法を話し合ったりすることで、子どもの記憶に残りやすくなります。
次に、「不審者への具体的な対応方法を教え、ロールプレイングで練習する」ことです。「いかのおすし」などの防犯標語を子どもと一緒に確認し、大声を出す練習や、安全な場所に逃げ込む練習を繰り返すことで、いざという時に体が動くようになります。特に、防犯ブザーの正しい使い方と「鳴らしたら逃げる」という行動を徹底させましょう。
そして、日頃から子どもとのコミュニケーションを密にすることも重要です。子どもが何でも話せるような信頼関係を築き、「何かあったらいつでも親に話していい」という安心感を与えることが、子どもの心を守る上で最も大切なことかもしれません。
この記事のまとめ
- 子どもの防犯対策 登下校では通学路の危険箇所把握が必須
- 不審者遭遇時は「いかのおすし」で具体的な回避行動を実践
- 防犯ブザーは定期的に点検し、すぐに使える場所に装着する
- 家庭内で防犯ルールを設け、親子で声かけ訓練を実施する
- 万が一に備え、様々な状況を想定したシミュレーションを行う
- 地域全体で連携し、子どもを見守る体制を構築する
- 親は常に子どもの話に耳を傾け、コミュニケーションを密にする
- 自宅の防犯対策も定期的に見直し、家族で共有する
- GPS機能付きデバイスで子どもの位置情報を把握する
- 地域の防犯活動や見守りボランティアに積極的に参加する
- 子ども自身の危機管理能力を高める教育が重要
- SNSなどでの安易な個人情報公開は避けるよう指導する
- 子どもの成長に合わせ防犯対策を定期的に更新する
- 地域全体で子どもたちの安全を守る意識を持つことが大切
- 子どもの防犯対策 登下校は親子の協力と地域の連携が鍵